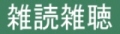『朝はミラクル』というOBCの朝の帯番組は、2005年4月4日に始まり、3年3ヶ月後の2008年6月30日に終わった。
かんべむさし氏が中崎くに子(これは作中の名)アナと組んでパーソナリティをつとめた。
その3年の体験をベースにした意欲的な書き下ろし長篇である。
関西の朝のラジオ番組といえば、朝日放送の道上洋三と毎日放送の浜村淳……町の食堂とかクルマで通勤する人はたいてたいこのどちらかを聴いている。この二大長寿番組(タイトルはこの二大番組に関わるフレーズでもある/作中にあり)の間に、リスナーとして団塊の世代を想定して割り込もうという企画が立てられる。
数回のランスルーで声量や滑舌を調整し、番組はスタートする。当初は無我夢中でスタートするが、半年ほど経過すると、さまざまな疑問や障害を感じ始める。作家なのかパーソナリティなのか、パーソナリティの役割、中崎アナとの掛け合い(作家としての興味が優先してしまうらしいとか)、放送作家を兼任しなければならぬ負担の大きさ……その他色々。
前半は1年間の季節の変化を背景に色々な事件やゲストのエピソードがちりばめられているが、やがて小説の雰囲気は「ラジオとは何か」「パーソナリティとは何か」をテーマとする思索的小説の雰囲気を帯びてくる。
読みながら、おれは「これは『笑い宇宙の旅芸人』のラジオ版だ」と気づいた。
ひとつはその文体にある。
主人公かんべむさしは、番組スタート時にこの体験を小説化すると公言する(本当にそうだったかは知らない)。そして小説化のためのメモを取り始める。このメモは《……》という形式で随所に挟まれるが、後半、その比率が高くなる。
疑問や悩みが生じるたびに、このメモを引用しつつ自問自答が繰り返される。
この自問自答は『笑い宇宙……』で延々と繰り返される登場人物3人(いずれも作者の分身)の笑いに関する議論と同質なのである。
さらに「メモを挟み込む」という手法が、特にメタフィクション的な面白さを狙ったものではなく、ストレートに書けばもっと長くなるところを凝縮させるために採用されているように読める。つまり小説としての完成度をある程度犠牲にしても思索の過程を記録しておきたい意志が優先しているとおれには読めるのである。※
ただし……決して堅苦しい理屈が展開されているのではない。
ラジオの世界を描いた業界小説(※※)としても、あるいは3年間のクロニクルとしても、そして「恋愛小説」としても、多面的に読める作品である。
前半で「かんべむさし」の試行錯誤と成長を描くのに対応して、後半では相方「中崎くに子」の青春期からのラジオ人生が描かれて、コンビとしてのバランスがうまく釣り合った頃に番組は終ることになる。
つまり全体の構成はちょっとせつない(疑似)恋愛小説でもあり、それがラストシーンにうまく生かされている。
※おれがこのような読み方をするのは、『笑い宇宙の旅芸人』は日本SF大賞受賞作であり、おれは選考委員のひとりであったからであろう。当時、候補作は非公表の方針だったが、ある程度知られていることなので、もういいだろう。この時、最終的に競り合ったのは『笑い宇宙の旅芸人』と筒井康隆『旅のラゴス』である。『笑い宇宙……』については「索引をつければお笑い辞典になる」が「小説としてはどうなのか」という意見もあった。完成度でどちらが上かは明かであろう。ただ「辞典一冊を作り上げる意欲というか執念」(むろんそれだけが評価されたわけではない)は評価されるべきだ。おれはその点で『笑い宇宙……』を評価したのである。
※※ラジオの世界を描いた作品に、藤井青銅『ラジオな日々』(小学館)がある。こちらは放送作家を主人公にした教養小説(成長小説)であり、青春小説でもある。
本HPに書こうと思いつつ、つい時間が経ってしまった。
かんべ作品と読み比べると面白いので、近日アップすることに。
(2010.1.12)
梶尾真治『メモリー・ラボへようこそ』(平凡社)カジシンの新作、中編2篇、背景や人物が重なり合っていて、全体は長篇でもある。
表題作は「老人SF」である。定年を迎えた桐生和郎は、仕事一筋で生涯独身、仕事以外の趣味もなく、仕事を離れると、特別の楽しみもなければ懐かしく思う思い出もないことに気づく。たまたま立ち寄った屋台の親父に、「思い出を移植してくれるクリニックがある」と教えて貰うのだが……。 メモリー・ラボとは、さまざまな提供者の記憶が貯蔵してあるメモリー・バンクで、その記憶の移植が可能だという。 桐生はある「おもいで」を移植してもらうが、その記憶のなかに現れる女性に会ってみたくなる……。 もう一篇「おもいでが融ける前に」……キャリアウーマンだった母(シングルマザーであった)に育てられた一人娘・笙子は、父親についてはいっさい聞かされなかったが、母が介護施設に入り、認知症になる前に、母の記憶、父親に関する記憶を知りたいと思いはじめる……。
「メモリー・バンク」という道具立ては、サイバーパンク以降の現代SFとしては、そう目新しくなく、むしろおどろおどろしさは抑制して、「他人の記憶が体験できる」程度の小道具として使われていて、物語はむしろ「他人の日記を読む」レベルで処理されている。メインは他人の「おもいで」を共有したことで生じる心の変化であり、それがハートウォーミングな物語を展開させる。
ボブ・ショウは「スローガラス」という小道具(その機能だけを描写し、原理的な部分については書かない)で、さらっと“泣ける短編”「去りにし日々の光」を書いた。他にも数編あるが、これだけが記憶されているといっていい。 カジシンはこれが「量産」とはいえないけど、高いレベルで次々に書ける。これはカジシンの名人芸である。
「スローガラス」に匹敵するアイデアだけでも、メモリー・ラボのみならず、エマノンその他多数……たいしたものだ。
(2010.2.7)
中山康樹『マイルスの夏、1969』(扶桑社新書)中山康樹氏のマイルス本……これは新機軸である。
中山氏には『マイルスを聴け!』を初め、多くのマイルス本があり、訳書に一級資料『マイルス・デイビス自叙伝』がある。しかし、まだこんな新機軸があった。
1969年は(日本では)ジャズがもっとも熱い時期だった。
ジャズ喫茶がいちばん賑わっていた時でもある。
個人的には、春に社会人になり、富山の工場に半年いた。田舎の雰囲気に耐えられず、日曜には富山市のジャズ喫茶『ニューポート』へバスで1時間かけて通っていた。アポロの月着陸があった。デビュー作になる短編を喫茶店で書いていた。流れていたのはハードバップである。
この頃、マイルスは何をやってたか。
翌年に大ブームを起こす『ビッチェス・ブルー』を録音していたのである。
『マイルスの夏、1969』は、「ビッチェス」に関わったジャズメン(ショーター、ハンクック、トニー・ウィリアムズ、ザヴィヌル、他大勢)、ロック・ミュージシャン(ジミヘン、マクラフリン他)、プロデューサー(テオ他)、作曲家(ギル他)、夫人(当時のベティ)など、数多くの人間の動きを前後数年間に渡って検証していく試みである。
いや、凄いのなんの。たとえば、マイルスの「今度いっしょにやろう」なんて一言が、人によっていかに解釈が違うか、多角的に検証されている。
マイルスが呼び寄せた者、偶然出会った者、去りゆく者、呼び戻される者……それぞれがビッチェスの録音に関わり、また次のジャズを試みたり、ともかく「ジャズが大きく変わる年」1969年を多角的に描いているのである。
「ビッチェス」の背景にこんなに複雑にして奇跡的なドラマがあったとは……。
そして、「ビッチェス」が出た70年、おれは山下洋輔トリオをライブで聴き、またニューオリンズ・ラスカルズを生で聴く。フリージャズとニューオリンズ・ジャズのライブに熱中しつつ、ジャズ喫茶「ハチ」ではハードバップ中心にLPを聴いていた。
電気楽器は体質に合わなかった。
「ビッチェス」以降のマイルスもあまり聴いていない。
しばらくして相倉久人氏のジャズ離れの書『ジャズからの出発』を読んだ。
1969年は、おれがジャズに熱中しはじめる年であり、ジャズが終わった年でもある。
この「熱い年」をよくぞここまで精密に記述してくださったものである。
(2010.2.7)
吉川潮『戦後落語史』(新潮新書)江戸落語の1945年(終戦後の寄席復活)から2008年(談志の喉頭ガンからの復帰)までの歴史を新書約200頁にまとめる。
無謀な試みに見えて、じつによくまとめてある。
わが関心事項のみ記す。
なんといっても戦後最大の事件(落語界に限らない、三島事件に並ぶ戦後最大の事件)落語協会分裂騒動である。
この事件の基礎文献は三遊亭圓丈『御乱心』であって、あと、好生、川柳(ガーコンはん)などの自伝、金原亭伯楽『小説・落語協団騒動記』『小説・古今亭志ん朝 芸は命、恋も命』、志ん朝一門の『よってたかって古今亭志ん朝』など10数篇の文献がある。
吉川潮氏が構成した『人生、成り行き 談志一代記』も。
本書では1章がさかれている。
談志が落語協会に戻る時の捨てぜりふ。
(談志が新団体のナンバー2になれないとわかった時に)
「俺たちは親睦団体じゃないんだ。落語協会や芸術協会と闘わなければいけないんだ。それを俺抜きでやれるのか」
「俺がいなくて三月もてばおなぐさみだ」
この部分は『人生、成り行き 談志一代記』からの引用である。
『御乱心』では「冗談じゃねェぞ。俺は三番目じゃやってられねェ。降りる!」である。※
いずれにしても、中心人物4人のうち、圓生、圓楽(完黙)、志ん朝(本人はほとんど語らず)は死に、残るは談志のみ。
吉川氏も立川流の顧問である(あとがきで「立川流史観」になっているのは否めない」と付記してある)。ただし吉川氏は落語三遊協会の記者会見をスポーツ紙の記者について行って聞いているキャリアの持ち主でもある。
面白く、しかし検証は難しい。
(2010.2.7)
※おれが談志発言にこだわるのは、先日の週刊朝日の書評欄だったと思う(図書館で目にしたので手元にない)、青木るえかという人が、本書のこの章は『御乱心』をそっくりまとめたもので、それだけに『御乱心』が名著であると確認できた、といった意味のことを書かれていたからである。
『御乱心』が名著であることに異論はないが(そして事実関係はだいたいその通りと談志も認めている)、肝心の部分は『人生、成り行き 談志一代記』のダイジェストである。このことだけちょっと申し上げたかったのです。
福田和代『プロメテウス・トラップ』(早川書房)注目の新鋭・福田和代さんの最新作。
空港ジャック(『ヴィズ・ゼロ』)、東京大停電(『TOKYO BLACKOUT』)、神戸沖を舞台にした海洋活劇(『黒と赤の潮流』)につづいて、天才ハッカーが国際サイバーテロ組織に挑む物語である。
主人公・能條は「プロメテ」と呼ばれていた天才ハッカー。MIT留学中に国家の中枢システムに侵入しかけて逮捕され、3年の実刑をくらった過去がある。今は日本でフリーのプログラマーとして退屈な生活を送っている。
ある日、能條は奇妙な誘いを受ける。過去の能條と「相性が良さそうな」サイバー・テロリストがいる。その捜査のために、偽造パスポートでの渡米を、謎めいた人物から半ば脅されつつ依頼される……。
この設定から、現実にあったミトニックとシモムラの電脳西部劇(『ハッカーを撃て!』)みたいなサイバー・ハードボイルドかと読み始めた。
読み違いではないが、話は直線的に展開する長篇ではない。
6章から成り、各章がそれぞれ独立したアイデア(偽造パスポートとかコンピュータによるチェスゲームとか)で書かれた短編でもあり、それぞれのアイデアが抜群に面白い。
しかも章ごとに、話は大きく方向を変える。これは「心地よい裏切り」の連続である。
しかも……いや、結末については暗示すら書かないけど、全体は長篇として見事に完結している。
システム・エンジニアとしてのキャリア、舞台となるロス取材の成果などが生かされた快作である。
(2010.2.7)
ジル・ブライス、バート・デービス『忘れられない脳』(ランダムハウス講談社)副題は「記憶の檻に閉じ込められた私」。
言葉の遊びからアイデアを得ることは発想法のひとつで、ずいぶん前だが、「健忘症」の対義語は何か考えたことがある。これをホラーSFにしたいとあれこれ考えていた。情報論とか決定論にこじつけて、無数の過去の事例にとらわれて身動きとれなくなってしまう男の話である。
落語会の後の席で、落語作家の小佐田定雄氏に話したら、「そんな難しい理屈考えてたら噺になりまへんで。落語にするならお稲荷さんにお願いしたらよろしいねん」……そして出来たのが、今では準古典ともいえる『神だのみ』である。この経緯は小佐田氏も著書で明かしている。おれの方は『メモリー・シンドローム』という短編にしたが、出来映えはいまひとつであった。1983年のことである。
それから30年近く経って、まさかこんな症例が「発見」されるとは想像もしていなかった。
1965年生まれのジルは8歳の時から日々の記憶を完璧に記憶して忘れられなくなる。
その記憶はコントロールできず、たとえば10数年前のテレビ番組を思い出すと、連鎖的に関連する記憶が細部まで蘇り、当時の喜怒哀楽までが再現されてしまう。それは大変な精神的ストレスなのだが、他人に説明しても理解してもらえない。
ジルは35歳の時(2000年)に思い切ってカリフォルニア州立大の脳科学者マゴー教授に連絡をとる。
そしてこの特異な症例は「超記憶症候群(ハイパーサイメスティック・シンドローム)」と名付けられた。
本書はそのジルが半生を語った「自伝」である。
「超記憶」能力があっても「丸暗記」科目は苦手だったとか、脳のシステムが特異らしいとか、症状が治療?された訳ではない。
彼女のストレスを救ったのは恋愛である。30半ばを過ぎて、ジルは、3歳年上・ふたりの子持ちの男性ジムと知り合う。彼と話していると「過去(記憶)への拘泥」が和らげられるのを感じ、結婚に踏み切る。
だが結婚生活は短かった。ジムは持病の悪化で、数年後にこの世を去る。
ジルはひとりでは生きていけないと錯乱状態に陥るが、やがて立ち直る。短いが幸せだった生活が記憶されているからである……
こりゃ、当然、拙作よりも遙かに面白く感動的だ。
小佐田はん、こんどは「人情噺」でっせ。
(2010.2.17)
日野皓正『逆光』(近代映画社)トランペッター・日野皓正の自伝的語り下ろし?
ジャズメンの本はどれを読んでも面白い。
「ハイノロジー」で物凄い人気スターになりながら、(ギョロナベにテレビ方面に誘われながらも拒否)、沼津に転居、その後渡米(子供4人を連れてである)、ニューヨークのジャズクラブで演奏しつつ、世界的トランペッターに成長していく。
しかし、決して裕福ではない生活まで明かしてある。
物語の大きな軸は「兄弟愛」であろうか。
日野元彦については高木信哉氏の「東京JAZZ」に詳しいが、兄から見た元彦像はまた少し違って見える。意外にもギャンブル好きだとか。
面白いエピソードや写真も豊富。
驚いたのが2008年に梅田の歩道橋でやってるライブに参入したエピソード。デキシー演ってるトランペットが、うまいじゃないかと、通りすがりに参入……あのヒノテルがと驚くが、このペットがMITCH(大阪~ニューオリンズで活躍している。映画「この世の外へ」で役者としても注目された)だったという。わかってたら自転車10分で駆けつけたのに……予告なしで始まるから面白いのだよな。
日野皓正は数年前に菊池雅章とのデュオを聴いて以来、ごぶさたしている。
新譜『寂光』を聴くことにしよう。
(2010.2.17)
筒井康隆『アホの壁』(新潮新書)アホという言葉は大阪では普通に口にするが、東京で使うとアホウ(阿呆)と蔑まされるような嫌悪感があるらしい。近年は上方のお笑いタレントが進出して多少希釈されたようだが、昔、藤山寛美が新橋演舞場「アホ祭り」なんて公演をやった時はたいへんだったらしい。
関東人はアホには過敏だが地震には鈍感である。以前、東京で仕事中に震度4の地震があって、おれは飛び上がったのだが、相手は平気で椅子に座っていた。
東京のアホは大阪の地震……と置き換えれば実感がわく。
そこで『アホの壁』である。書いたのが筒井さんとなると、これは震度7の激震ではないか……
本書でのアホとは「文化的な価値など皆無の、つまらない」言動である。ひとはなぜ良識とアホの間にある壁を簡単に乗り越えてアホ側へ行ってしまうのか。
それらの具体的な事例はそんなに列挙されていない。
アホの「ものいい」「行動」「喧嘩」などについて心理学的・社会学的・哲学的論考がなされるが、これを自分の知る範囲のアホに当てはめると、事例はいくらでも思い出せるし、あ、あのアホはこういう理由でアホだったのかと、目からウロコ、あれもこれもたちまち氷解していく。
「アホの計画」なんて、ボンクラ・サラリーマン時代のアホ(上役多数)を思い出すと、なるほど合点……と、じつに痛快なのだが、半ばを過ぎるあたりから、それは自分の過去の言動や現在の内面にまで迫ってくるのである。
うへ、おれはこんなにアホだったのか……
それだけに、終章は感動的である。
終章だけ立ち読みしてはいけません、最初から読んでいってこそアホから救済されるのである。
(2010.2.23)
梶尾真治『ボクハ・ココニ・イマス 消失刑』(光文社)『メモリー・ラボへようこそ』に続いて、カジシンの今年2冊目。コンスタントにハイレベルの仕事を継続している姿勢には敬服する。
主人公はつまらぬ女性に関わったことで傷害事件を起こし、実刑を受けるのだが、刑務所への収監か「消失刑」か選択できるという。
消失刑とは(実験段階の刑事罰で)、行動は自由だが、他人からは「盲点」にあって見えない、会話や通信は禁止、行動範囲も制約され、食事だけは給食を受け取りに行くという。
これは、久しぶりに登場する「透明人間もの」である。
刑罰としての透明人間というのが秀逸な着想で、これは(作中には)シルバーバーグの作品に出てきた「無視刑」がヒントとある。……これは『***』だったかな? 長篇のなかの1エピソードだったと思う。(※)
本来だと、これは短編のアイデアのように思えるが、これがカジシンの手にかかると、「孤独」という大きなテーマが浮かび上がる。
例によって熊本の町並を背景に、交通事故の危機、過去の同僚などの目撃、ホームレス狩り、透明化装置の故障、やがて巻き込まれる不気味な失踪事件……と、物語は見事に展開、長篇に仕上がっている。
おれは熊本には何度も行っていて(九州ではいちばん訪問回数が多い)、熊本の町並はだいたい知っているが、それでもカジシン作品を読むと、やっぱり風景描写が新鮮で、また久しぶりに行ってみたくなる。
この作品でも、知らない場所、知っていて気づかなかったところなど、随所に出てくる。
藤沢周平に「海坂藩地図」があるように、カジシン作品の熊本地図を誰か作ってくれないものだろうか。
(2010.2.23)
※これは小生の勘違い。30年以上前に訳された短編であり、しかもその短編をヒントにしたのではなく、独自に思いついたら類似したアイデアが先にあり、作中で敬意を表したということらしい。後日確認して再度訂正することに。(2010.4.26)
※※ということで、(山岸真さんに教えていただいた)「奇想天外」1977年4月号掲載のロバート・シルヴァーバーグ『見えない男』を確認。確かにこの短編であった。
これは確かに読んでいたが忘れていた。耄碌の可能性が高いが、たぶん、それほど感心しなかったからと思う。「Invisible Man」にされる刑(作中では「不可視刑」)が単に社会的制度によるもの(したがって当時でも実現可能……したがってカジシンが「無視刑」と表現しているのが実に的確)で、一種の「いじめ」を拡大したくらいにしか受け取らなかったのだと思う。(今読むと、やはり傑作であると思う)
「消失刑」の設定はまさに透明人間化で、したがって展開もまったく別物となる。
ついでに70年代後半の「奇想天外」を拾い読みしたが、この時代、熱気があったなあと思う。この当時と変わらぬテンションを維持しているカジシン、やはりたいしたものだ。(2010.4.28)
両角長彦『ラガド 煉獄の教室』(光文社)第13回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作である。
都内のある私立中学の教室で殺人事件が起きた。
犯人は中年男。女子生徒のひとりに切りつけ、もうひとりをメッタ刺しにして殺害した。
犯人の男の娘は、この教室にいた生徒で、3月前に自殺している。いじめが原因らしい。
だが……殺されたのは自殺した生徒と唯一仲のよかった女生徒である。
警察は地下体育館に40人の席を作り、事件の時の犯人と生徒の動きを再現しようとするのだが、被害者の女生徒役を命じられた婦人警官は、証言と行動に奇妙な食い違いを感じる……。
このように設定を要約しても、この作品の面白さは伝えにくい。
マスコミの取材の会話や、生徒の証言、調書、不気味なモノローグなど、色々な視点での描写が入り乱れて、さらに警察とは別に、学校経営者の秘書と、テレビ番組のディレクターが別個に事件を追い始める……しかし、これが読みにくくはなく、むしろ心地よい困惑に読者を巻き込む。ユニークなのは約100枚!の配置図(40人と犯人の配置と行動を図解)で、この図と40人の証言とが集中するクライマックス部分はすばらしい。
小説宝石3月号に選者のひとり・綾辻行人氏との対談があり。
そこで明かされている範囲でいえば「広義のミステリー」であり「SF、ホラー指向が強い」作品ということになる。
「ラガド」という言葉の由来とビジョン、最後に明かされるものは、SFのセンス・オブ・ワンダーと同質で、堂々たるSFと評価してもいいと思う。
作者は冒険小説や本格SFの構想もお持ちのようで、楽しみな新人(1960年生まれだから、ちょっと遅れてきた大型新人)の登場……などと書くと、ちょっと白々しいか。
両角長彦という新人登場だが、SFファン(特にSFマガジンのリーダース・ストーリーをお読みの方)なら、三枝蝋という名を覚えておられるのではないか。常連といっていい名手である。じつはおれは10年以上前から知っているのである。
ショートショートや短編はうまいのだが、できれば長いものを書いてほしいと願っていた。見事な達成である。
(2010.2.23)
奥村彪生『日本めん食文化の1300年』(農文協)料理人にして料理研究家である奥村彪生氏が1300年の日本の麺文化を網羅した大著。
奥村氏は関西ではテレビの料理番組でおなじみの方である。
石毛直道先生主催の花見会で顔を合わせたり、某寿司店でお目にかかったりする。
ただ、麺関係の場所でお見かけする機会はなかった。
その奥村氏が博士号を取得した論文をベースに日本の麺文化研究をまとめて、たいへんな労作である。
巻頭に石毛先生の推薦文があり、そこに奥村氏の研究方法のユニークさを簡潔に述べられているが、それをさらに要約すると、次の4点である。
①過去の資料を調査する。②現地調査する。③その成果を復元する(実際に作る)。④それを食べたり分析して考察する。
①②はオーソドックスな方法だが、ともかく徹底している。古文書からサザエさん(中華そば→ラーメン→即席麺がいとどんな頻度で登場するかなど)まで、膨大な資料がチェックされているし、北海道から沖縄まで「現地調査」がなされている。
しかし、ともかくユニークなのは③④であって、これは料理人としての技量が十全に発揮されている。
たとえば日本最古のめん「さくべい」については、時代によって変化が見られるところから2種類が復元されている。
各地の食べ歩き記事としても面白く、おれの最大の関心事であった「だしの東西の境界線」につていも、名古屋中心の「溜醤油圏」が明確にされているし、東西の共存域も一般にいわれているよりは広く、米原~静岡に拡大されている。日本海側の調査もぬかりがない。この境界地図はおれの経験(おれの場合は立ち食いだが)から、いちばん納得できるものだ。
その他、そうめんの「新」「古」「古古」の食べ較べテストによる俗説の検証とか、「めん食地帯」による日本列島のゾーン分けとか、面白い考察がいっぱい出てくる。
これは今後の麺文化研究の一級資料となるだろう。
唯一ものたりないのは……立ち食いうどんに触れられてないところだ。
共同研究を持ちかけよかしらん。
(2010.2.28)
[SF HomePage] [目次] [戻る] [次へ]