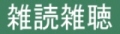アルジス・バドリス『無頼の月』(SFマガジン1961年8〜11月号)
新発掘された小松左京氏の1961年のコラムを読んで、半世紀ぶりに再読した。
小松左京マガジン45号で小松さんが『無頼の月』に触れた無署名コラム(事情はこちらに)が紹介されている。
『無頼の月』はSFマガジン1961年8月号〜11月号に4回に渡って連載されたが、本にはなっていない。読んだのは高校1年の時である。
1959年(米ソが宇宙開発でしのぎを削っていた時代)、アメリカの宇宙船が月面の裏側に謎の構築物を発見する。アメリカはソ連に先駆けてこの構築物を調査するために、ホークス博士の開発した「物質電送機」で月面に調査員を送るが、調査員は「構築物」に入ったとたんに次々死亡する。ホークスは装置を改良して、「元の体」を残し「複製」を電送するが、複製が死亡すると(たぶんその死の恐怖で)地球の装置にいる人間は発狂してしまう。そこで調査員としてパーカーが選ばれる。パーカーは義足の退役軍人で自殺願望がある。死に恐怖を感じないのである。
「君は自殺型だ」ホークスはパーカーにいう。「わたしは殺人型だ。……われわれは、すばらしいコンビになるぞ」
ここまでが第1回。
月面裏側に発見された謎の構築物という設定がぞくぞくさせる。
次号を待ちかねるように読んでいった記憶があるが……連載を読み終えて、なんだかひどい欲求不満が残ったのも覚えている。
当時大学生だった兄とずいぶん議論したものだ。
おれの不満は「構築物の正体が何かまったく解明されないまま」である点に尽きる。
兄の読み方は「この作品の眼目は、物質電送機で何度も繰り返して死を体験するという設定にあるんだよ」というものだった。
結局、おれの不満は、後年連載された『ソラリスの陽のもとに』で、はるかに高いレベルで解消されることになるのだが。
今回再読して(今の時点で評価するなら)、物質電送技術が開発されたなら、ロケット技術どころではなかろうにと思うし、月面の謎の構築物と電送技術とが結びついていないなど、技法上の欠点が目立つが、こちらの読み方が浅かったのも痛感する。
物語の軸は月面調査ではなく、多数の犠牲者を出しても平気でプロジェクトを進めてきた「殺人型」科学者ホークスの変化にあるのだった。
最初読んだときに、女性関係の描写がじゃまだなと(たぶん読み飛ばしたか忘れたか)感じたが、ホークスが少年時代を女性に告白する描写などの方が眼目なのである。
第1回を読んで、小松さんはどう思ったか。
上記コラムでは「(SF的な設定もさることながら、殺人型と自殺型の人物の出会いが)はりつめた筆致で描かれており……ヘミングウェイ、メイラーなどの行動派文学のテーマを意識して踏襲しているように見える。」さらに「この作品で興味があるのは、こういうテーマをSFに持ち込んだのではなて、逆にこういうテーマの展開のためにSFという形式を利用しようとしているように見える点である。」「純文学という一種のリアリズム小説は、状況設定に当たって現実の制約をがんじがらめにうけ」「鎖をひきずって歩かなければならない」「その点SFの方は、いくらでも極端な状況設定が可能であり」「人間追求の実験装置としてははるかに便利だ。」
さすがという他ない。
これは、むろん、数年後の「文学の科学」につながる。
この号(SFマガジン1961年8月号)には第1回SFコンテストの入選発表があり、「努力賞『地には平和』小松左京」とある。
小松さんはすでにこうした方法を自覚しており、したがってバドリスの筆致に共感を覚えたということなのであろう。
(2012.5.1)
副題は「金融腐敗=呪縛の検証」……第一勧銀の不正融資など一連の「金融腐食」事件を追ったノンフィクションの再刊だが、ここでは「原辰徳の女性問題」事件の「番外編」として紹介。
この本、高杉良『金融腐食列島』『呪縛』と同じ事件を扱っているが、日銀と銀行の癒着、証券業界の腐敗まで、バブル崩壊後に明るみに出た一連の金融事件を検証するノンフィクションである。
この本の存在は知っていて、(高杉良の小説は読んだが)そのうち読もうと思いつつ、文庫化されたのに、気がつけば絶版になっていた。
今回、七つ森書館から再刊された。
「著者」は「読売社会部清武班」……延べ41人の読売の記者が500人以上の関係者を取材、金融界の「腐敗の構造」を追究した。取材チームの中心にいたのが読売社会部次長の清武英利氏であり、そのチームは「清武班」と呼ばれた。
取材力、分析力、並ではない。たとえば「自殺者」の人物像を検証するために、親族・同級生・同僚など数十名に(取材拒否を含めて)当たっている。そして見事に「人物像」を浮かび上がらせる。
爆笑エピソード満載。ノーパンしゃぶしゃぶなんて前座。
一例あげれば、銀行役員(接待する側)が高級料亭で待っていた。日銀の局長(接待される側)が来て「ちょっと失礼」と奥の部屋へ行ってしまった。しばらくして、日銀局長は浴衣を着て現れ、浴衣の裾をまくって、床の間を背にした。……日銀局長はそれほどまでに「高級料亭」の常連なのである。
いやはや。
こうした膨大な取材データをまとめつつ、金融業界の「腐敗構造」を解き明かしていく。
恐るべき力量である。
清武英利氏は読売棒振団みたいなつまらん組織に行くべきではなかったのよなあ。
清武氏は再刊のあとがきにいう。ナベツネの球団私物化を訴えた背景には「トップの理不尽を告発する際、『おかしいじゃないですか』と幹部を追及した第一勧銀中堅幹部の一声が心のどこかにあったのだろう」と。
清武氏のジャーナリストとしての今後の活動を期待する。
ちょっと脱線の話。
この事件の前半の主役のひとりは総会屋・小池隆一である。
当時(1997年頃)、おれはよく小池隆一に似ているといわれた。複数の、相当数からである。「あの高笑いしている顔をテレビで見るとギョッとしまっせ」(谷甲州)……そんなに似てたかなあ。性格は真似できんけど。今では頭髪も変わっているから、もう間違えられることはないだろうけど。
で、「原辰徳の女性問題」である。
1988年、原辰徳がアルバイト女性とねんごろになった頃、第一勧銀の株主総会に小池が食い込んだ。
1995年、阪神大震災の時、女性は姿を消した。この頃から小池への巨額の迂回融資が始まった。
時代は重なっている。
清武氏にはがんばってほしい。
おれ(小池隆一)は引退だけどね。
(2012.6.23)
年間SF傑作選 2011年の18編
大森・日下氏が編集する年間SF傑作選も『虚構機関』以来、もう5冊目である。
今回も面白い短編が集められているが、ともかく「SFの広がり」と「若返り」を実感する。
一時期(10年ほど前の数年間)、文芸家協会の『現代の小説』の委員を務めていたので、雑誌掲載のSF周辺の短編を全部読んでいた。もう今はその体力はない。ただ、その頃の記憶と較べても、SF周辺での作風の広がりに驚かされるし、それらが新世代の書き手、ジャンルにとらわれない作家によるものであるところが新鮮だ。
このような傾向の代表格は円城塔だろうが、石持浅海「黒い方程式」とか宮内悠介「動く家にて」などの、SFかミステリーか定義不能の作品などが面白い。
一方で神林長平や川上弘美作品など、「この年」を反映した堂々たる短編もある。小川一水さんなんて今やベテランの風格を感じさせるなあ。
個別に感想を述べるとキリがないので、一編だけ。
巻末の第3回創元SF短編賞受賞作、理山貞二「<すべての夢|果てる地で>」は、年間傑作選の中でもベスト級の傑作である。新しい才能の出現を喜びたい。
冒頭のマンション襲撃の場面がいい。マンションの一室でネットでの株取引をしているKはある組織の襲撃を受ける。Kは逆襲に転じる。この組織の背後にはウォール街の投資ファンドが関与しているらしい。雰囲気は量子コンピュータで構成された世界を舞台とするサイバーパンク調だが……ニューヨークへ飛ぶ機内でKが読むのは「報酬」をつぎ込んで入手した「紙の書物」であり、SFなのである。この「SF」が間奏のように挿入される。
現実?の世界と物語の世界が交互に語られるのだが、「想像とはヒルベルト空間の別の場所を観測する行為である」という量子論的仮説が、「物語が宇宙に干渉する」にまで拡大される、まさにメタSFなのである。
サイバーパンク調の現実?描写と間奏部分に(作者は相当なSF読みのようである)多くのSFへのオマージュがちりばめられているが、マニア的な描写ではなく、決してジャマにはならない。量子論的仮説の構築力はいいし、多くの登場人格のネーミングも秀逸。これらが伏線となって、最後に示されるKの姿は感動的である。
応募時期から考えて、この作品が2011年夏以前に執筆されていたのは間違いなく、結果として、2011年にふさわしい作品となった。ある意味で「奇跡的」な作品でもある。(※)
ええっと、拙作「巨星」も収録されておりますのでよろしく。おれがいちばんの古株である。
(2012.7.10)
※先日、作者・理山さんにお目にかかる機会があった。作者のおっしゃるには「構想は以前からあり、下書きは2011年7月以前から始めていたが、7月の出来事が構想に影響した面もある」とのことであった。このことは、むろん作品の評価を変えるものではありません。(2012.7.12)
副題は「SF作品に見る静岡県」
たいへん面白いSF論の試みである。
2011年のSF大会は静岡で開催された。プログレス・レポードには「静岡とSF」をテーマとする記事が掲載されたが、ブログでも「静岡SF大全」というページが設定され、日本SF評論賞受賞の評論家チームが中心となって色々な記事を掲載した。
その企画をベースとして新たに書き下ろされたのが本書である。
宮野由梨香さんが巻頭の総論で(過不足ない文章なので要約するのは失礼なのだが)「本書は、SFを通して「しずおか」という土地の精霊、ゲニウス・ロキを再発見しようという試みなのである」と述べ、近代科学を背景とするSFの始祖が「フランケンシュタイン」であるのに対して、スペキュレーティブ・フィクションとしてのSFの始祖「竹取物語」を論じている(富士市の竹採公園の「竹採塚」が発祥の地という説による)。また「ご当地SF」として星新一「羽衣」(三保の松原)を題材に羽衣伝説を論じる。
これは正攻法による静岡SF論だが、アプローチは多彩。
ヘドロを直視した「ゴジラ対ヘドラ」(鼎元亮)、「日本沈没」から静岡の風景を論じたり(石和義之)、アニメの舞台としての静岡(関竜之)、ガンダム世代の静岡地勢学(磯部剛喜)と、まったく遠慮ない論じ方である。
作家論として、ご当地作家・杉山恵一(高槻真樹/この作家についてはまったく知らなかった)、藤枝静男(岡和田晃)、瀬名秀明(横道仁志)。
それぞれ、たいへん面白い。
「しずおかSF」の作品リストも充実している。
ひとつ贅沢な要望をいえば、「都市論」的なアプローチのものがほしかった。具体的には浜松。浅倉久志氏が暮らし伊藤典夫氏が育った街としての浜松である。小松左京と京阪神の風土、カジシンと熊本が切り離せないように、両氏が浜松でどのようにSFと出会ったのかには興味がある。ただ、浅倉氏も伊藤氏も翻訳家で、浜松について(自伝的なことは)ほとんど書かれていないし、語りたがらない雰囲気もあるからなあ。
こうした試みは、また別のSF大会開催地でも、ぜひ続けていただきたいと思う。
(2011.7.10)
蓮見恭子さんの『女騎手』『無名騎手』につづく長編サスペント。
蓮見恭子さんは創作サポートセンターの生徒だったひとり。10年以上前、ファンタジックな長編を何度か読ませていただいた。文章は筋がよく、アクション場面の描写が生き生きしていたが、書きたい場面とあまり好きでない場面にムラがあったような記憶がある。
その後、ミステリー系のコンテストでは何度も最終選考に残ったが、いま一歩という時期が続いた。
しかし、着実に力をつけられた。
『女騎手』で横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞。これは和製ディック・フランシス登場と話題になった。
つづいての『無名騎手』も競馬ミステリーの佳作。競馬界、特に厩舎や騎手、馬主の世界が丹念に書き込まれていて、独自の作風が確立されつつある印象だった。
本欄でも紹介をしたいと思いつつ、家庭事情がややこしい時期だったので失礼してしまった。
で、今度の新作『ワイルドピッチ』は、なんと野球ミステリーである。
高校球界の世界を背景にした野球小説・青春小説であると同時に、格差社会、生活保護の不正受給など社会問題がからむ悲劇的な事件を描くサスペンス・ミステリーでもある。
高知の野球の名門高校のエース・武蔵(地元高知出身)は肘に不安を抱えている。2年生の時期エース候補・大樹(東京から来た特待生)は精神的に弱く、寮でいじめにあっているらしい。夏の高校野球では甲子園出場を決めたが、イジメが問題化すると出場辞退になりかねない……。
大樹の母は東京の高級住宅街にひとり住む主婦(主人は海外勤務)でステンドグラス工芸を趣味にしていた。彼女はひとり息子を心配して、精神に不調をきたす。
一方、八丈島沖の洋上で、トランクに詰められた女性の死体が発見される。死体には珍しいガラスの破片が付着していた。
捜査網が狭まっていく過程と、甲子園で勝ち進んでいく過程が交互に語られていくのだが……。
ミステリーとしては複雑なトリックが使われているわけではない。
高校野球と貧富の格差という、およそ関係なさそうなテーマが重ねられて、不思議なサスベンスを生み出す。この構成は見事だ。
多彩な人物の造形もきちんと書き分けられ、特に武蔵の「土佐弁」がいい効果をあげている。
蓮見さんはまた世界を広げたようだ。
(2012.7.22)
副題は「遊郭経営10年、現在、スカウトマンの告白。
飛田新地については、昨年読んだ『さいごの色街 飛田』が出色のノンフィクションであった。
だが、まだ知りたいことが色々残った。たとえば楼主(元楼主)に会いに北陸まで行くが、なぜ飛田から「追放」されたのかは書かれていない(おれは、聞き出せたものの、タブーに触れるので書けなかったと感じた)。
そのようなタブーがまだまだあると睨んでいる。
そこに「遊郭経営10年、現在、スカウトマン」の告白である。
さらにタブーに踏み込んであるのかと期待して読んだのだが、結論からいえば、ほとんど期待はずれ。
作者は、繊維問屋に勤める(たぶん30歳くらいの)独身サラリーマンだったが、リストラで失職、父親の生命保険が入った時に、裏社会に関わりのある同窓生が、1千万で飛田遊郭の経営権を買わないかと持ちかけてきた。
それから10年間、「親方」として働いた体験談である。
内容は浅い。おそらくゴーストによる聞き書きで、手慣れた文章だが、『さいごの色街 飛田』に較べると「腰の入り方」が違う。譬えはは悪いが、飛田流「チョンの間」で書き上げられた印象だ。
面白いのは開店までの費用と手続き、客引きの「オバちゃん」に関する記述、ホスト上がりの親方が増えたがたいてい失敗するといった話くらい。あとは『さいごの色街 飛田』を超えるところはない。
たとえば、こちらが知りたい「警察との関係」「規則を破った親方への制裁」「風俗からの引き抜きでヤクザに拉致された時の解決金」など何も触れてない。
筆者は10年で店を手放し、スカウトマンに転じたというが、いくらで誰に売ったのか、10年間の収支はどうだったのか、毎年の確定申告はどうやったのか……まったく書かれていない。
現在「スカウトマン」という。『さいごの色街 飛田』のあとがきには、「新手の周旋屋が増えて」利益配分が変わり、「女の子が稼働する限り」「経営者の取り分の三割から半額のマージンを強いられる」とあるが、作者はどうやら「周旋屋」に転じたらしいのである。
だが、そちらの実態も書かれていない。
誰か、もう少し踏み込んでくれないかなあ。
(2012.9.19)
[SF HomePage] [目次] [戻る] [次へ]